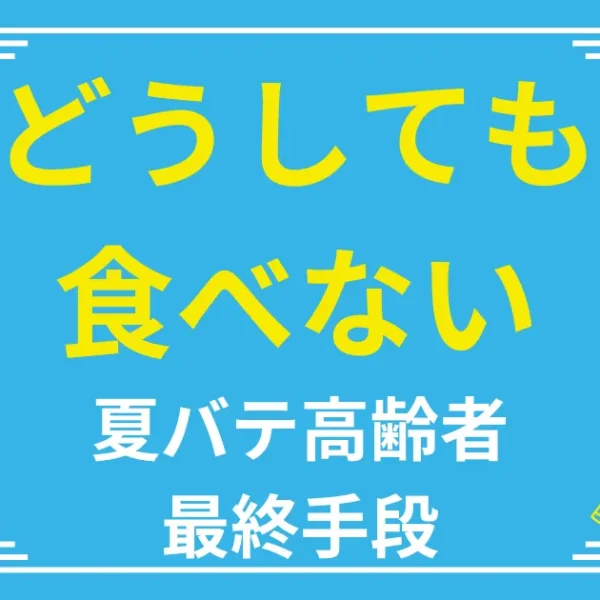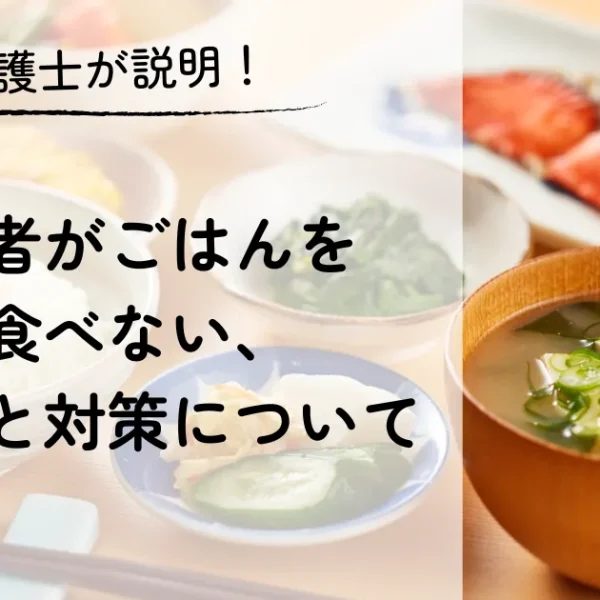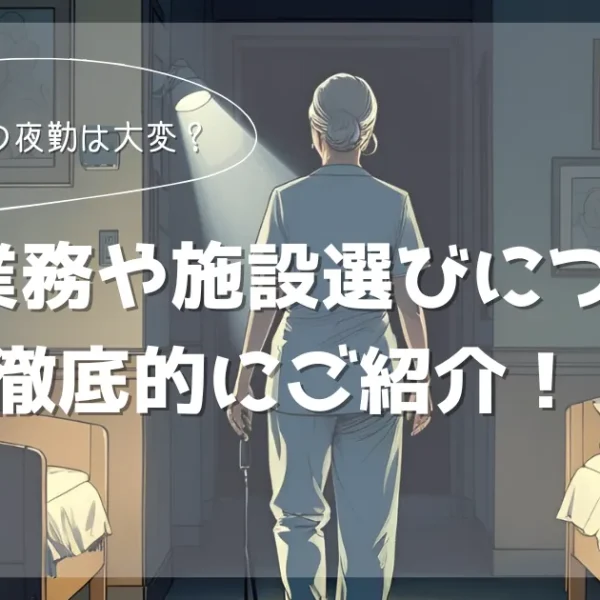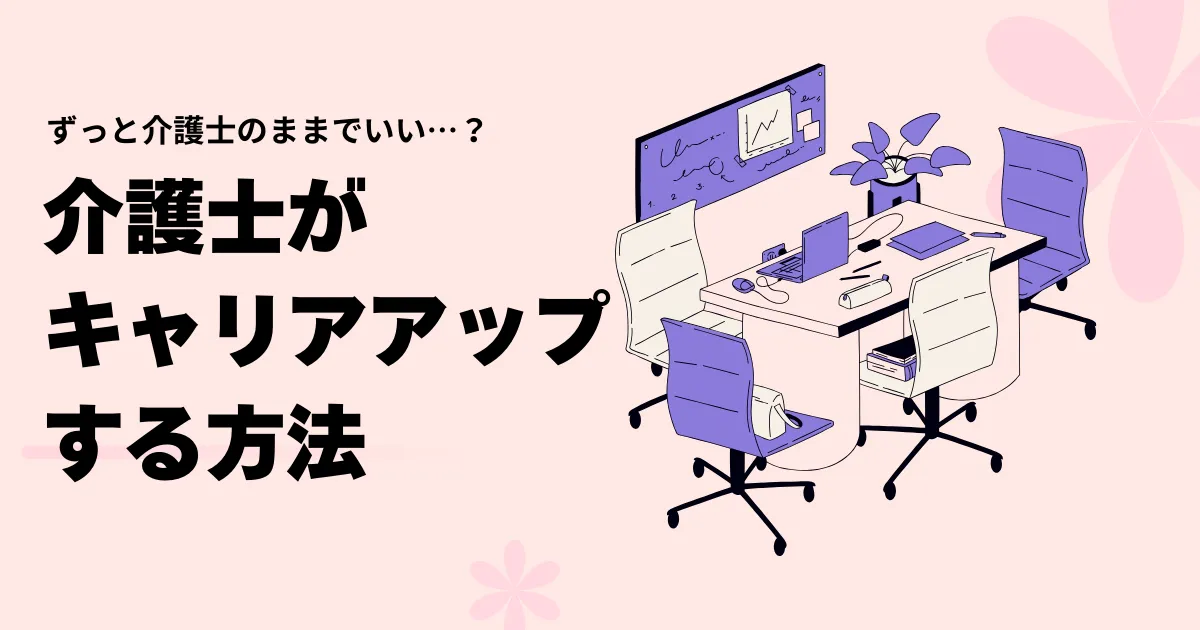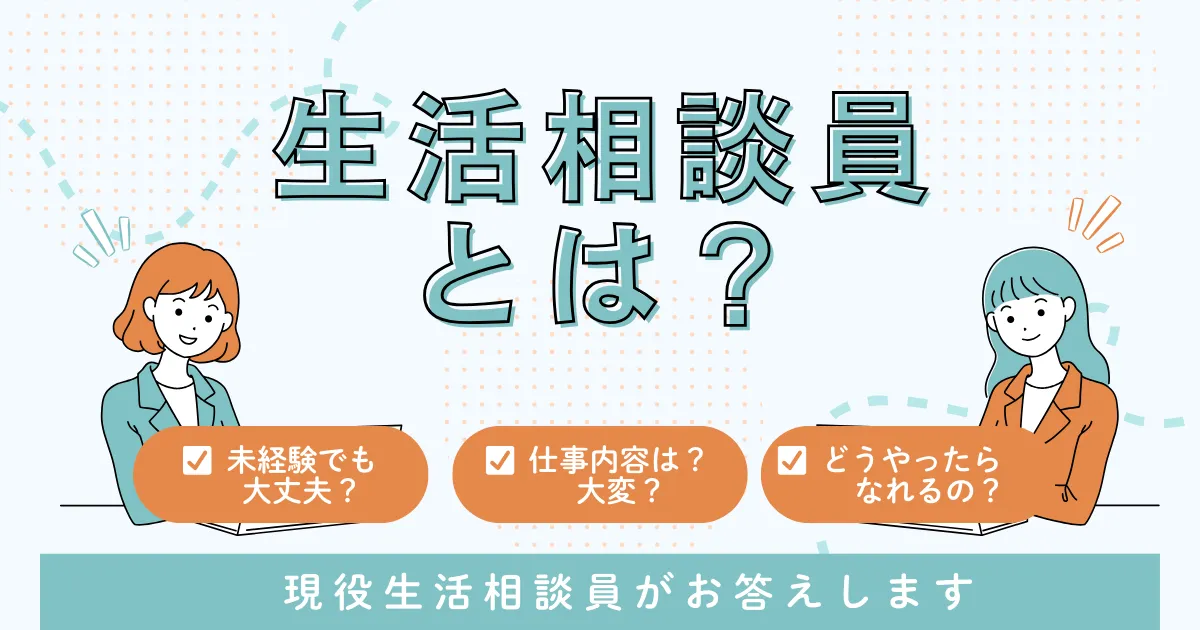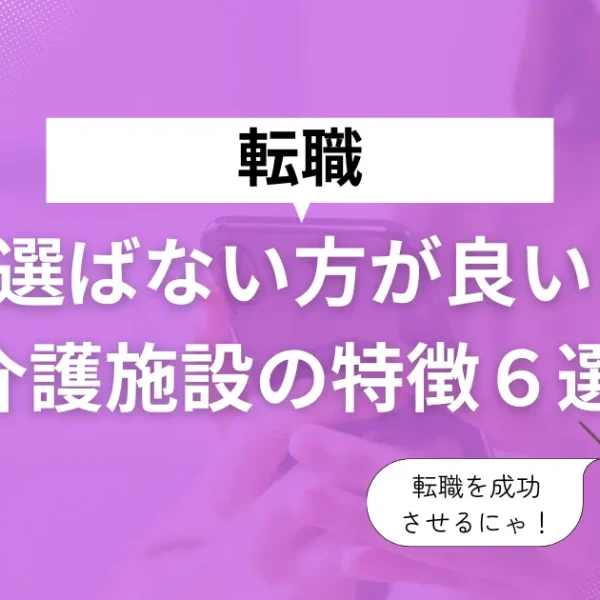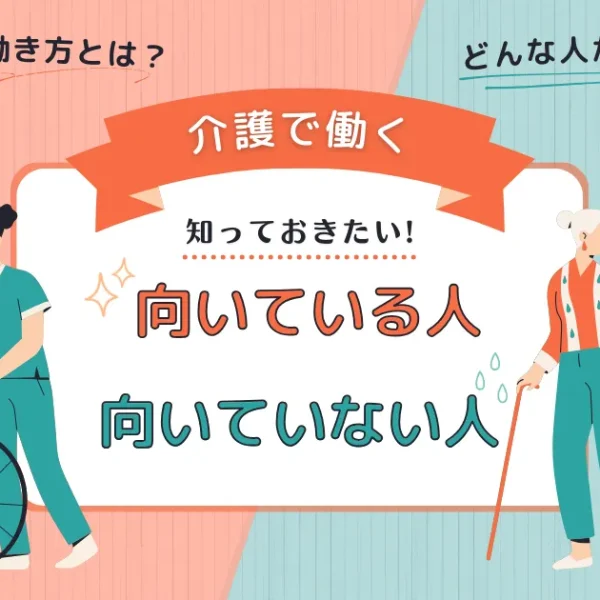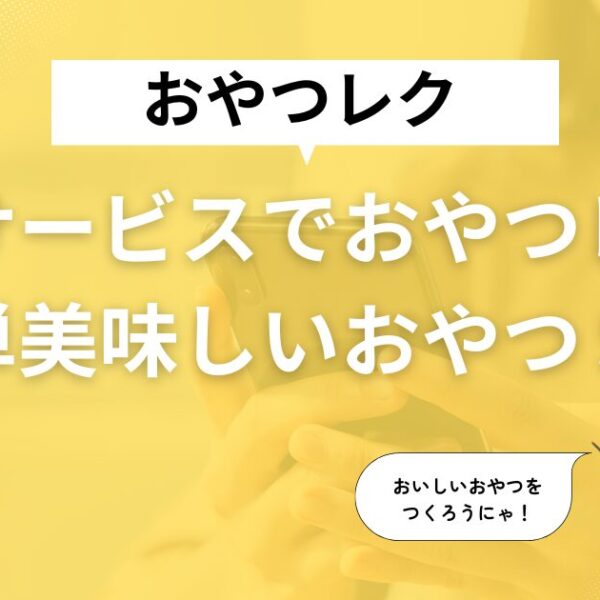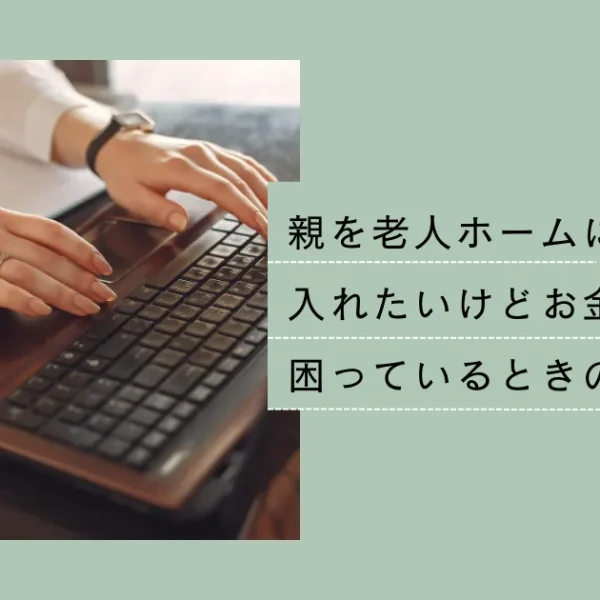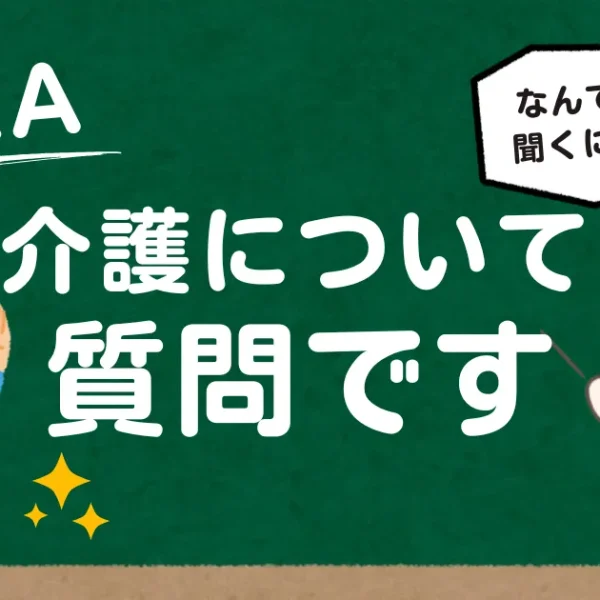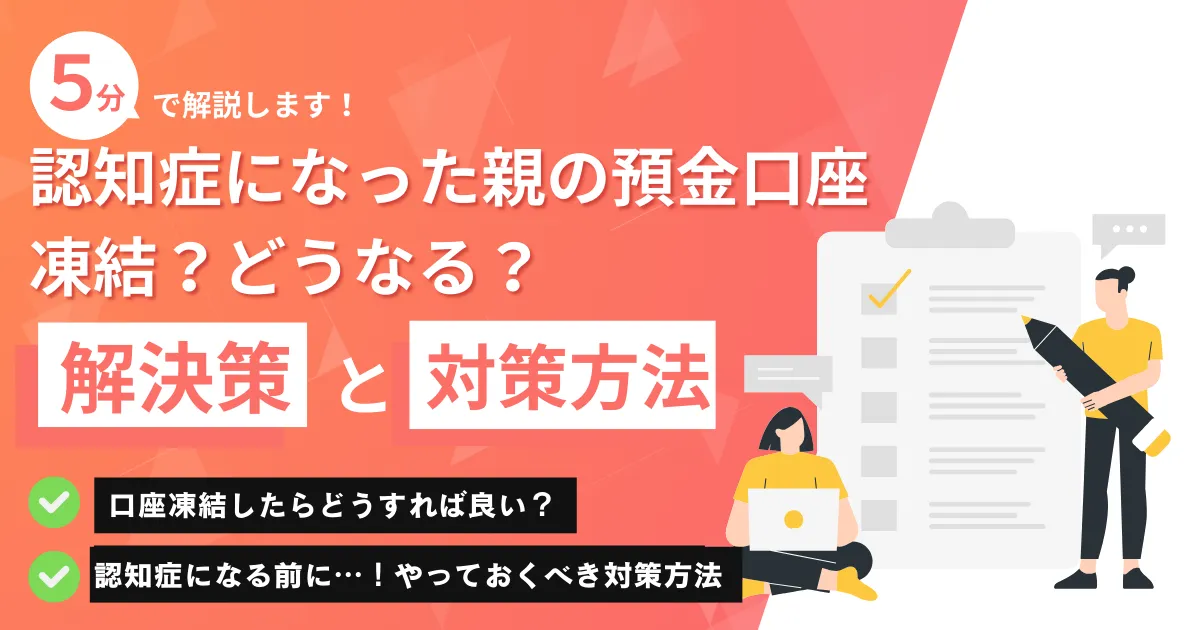
※本ページはプロモーションが含まれています
親が認知症、若しくは認知症の疑いがある場合、困るのは”金銭管理”ですよね。
「親が認知症で口座のお金を引き出せない…」
なんて状況になってしまうことも…。
判断能力のない認知症の方の預金口座はどうなってしまうのか。
またどのように管理をしていくべきなのか、解説していきます。

ひとつずつ解決していきましょう◎
・親が認知症で本人が口座からお金を引き出せない
・認知症の親の口座管理の仕方を知りたい
・もし凍結してしまったときの解除方法を知りたい
目次
親が認知症だと口座は凍結される
結論を言うと、親が認知症だと口座は凍結されます。
なぜ凍結される?
認知症により判断能力が低下していると、取引の安全性(詐欺等)を疑わないまま実行・契約してしまうなどリスクがあります。
個人の財産を、口座凍結という手段で守るというわけです。
銀行が知るきっかけ
銀行側は口座名義人が認知症であることを知るきっかけがあります。
・家族や本人が認知症のことについて銀行側に相談した
・本人が銀行手続きにて氏名や生年月日を間違えるなど、手続きが正常に出来ないとき
・家族が本人のキャッシュカードを使ってATMで1日の限度額いっぱいを引き出した場合
・突然の多額の振り込みがあった場合
などの場合に銀行側は口座名義人が認知症であることを知り、口座凍結に至ります。
口座が凍結したときの対処法
口座が凍結した場合、成年後見制度を使うことで凍結解除されます。
むしろこの方法しか凍結解除方法がありません。
成年後見制度では任意後見人か法廷後見人がありますが、認知症になった後は法廷後見人しか選べません。
法廷後見人は弁護士や司法書士が担い、口座名義人に替わって財産管理や契約行為を行えます。

口座凍結させないための対策!
口座が凍結する前に出来る対策は何かあるのか?
ありますが、どれも認知症になる前に手続きが必要です。
今からお伝えする2つの対策は、親が認知症になったときに家族または選ばれた方が継続して財産管理できるものとなります。
任意後見制度
任意後見制度とは成年後見制度の一つで、認知症になる前にもしもの場合に備えて財産管理などしてくれる後見人を自分で選ぶことができる制度です。
✓自分で後見人を選ぶことが出来る
✓自分の希望を契約内容に反映しやすい
✓認知症になったら任意後見制度は選べない
✓死後の事務処理や財産管理は依頼できない
任意後見契約制度について詳しく解説されているHPはこちら↓
家族信託の契約を結ぶ
家族信託を結ぶことで不動産や金銭管理などを家族に任せることが出来ます。
また、財産の分配方法を事前に決めておくことができるため相続時のトラブル軽減にも繋がります。
✓ 認知症などで自分で管理できなくなった場合に安心
✓ 財産の分配方法を事前に決めておくことで、相続時のトラブル回避に繋がる
✓ 適切に設計することで、相続税や贈与税の負担を軽減ができる場合がある
✓信託契約の作成や専門家への相談には費用がかかる
✓信託契約の内容や手続きが複雑であるため、理解するのに時間がかかることがある
特に法律や税務に関する知識が必要
✓受託者には財産管理の責任があるため、適切に管理できない場合、法的な責任を問われることがある
✓変更が難しい
相談先は専門家へ
任意後見契約や家族信託は、家族内だけで行うことは出来ません。
弁護士や司法書士などの専門家へ相談、依頼し、手続きを行うことが、
正しい財産管理に繋がります。
費用はかかりますが、行っておくことでトラブルなどは避けることが出来ます。
後見制度について知りたい方はお住いの地域包括支援センターまたは社会福祉協議会に相談するのも手です。
まとめ
・親が認知症であり、そのことを銀行が知った場合、口座が凍結される
・口座凍結した場合は成年後見制度を使うことで凍結解除される
・口座凍結対策として、任意後見制度か家族信託を結ぶことがある(認知症になる前に)
親が認知症になる前に、事前に対策を打つことがスムーズな相続にも繋がります。
親が認知症になってからであると相続対策できなくなります。
口座管理にとどまらず、不動産や資産の売却などできなくなるため、認知症になる前に本人と話し合って相続対策することをオススメします!